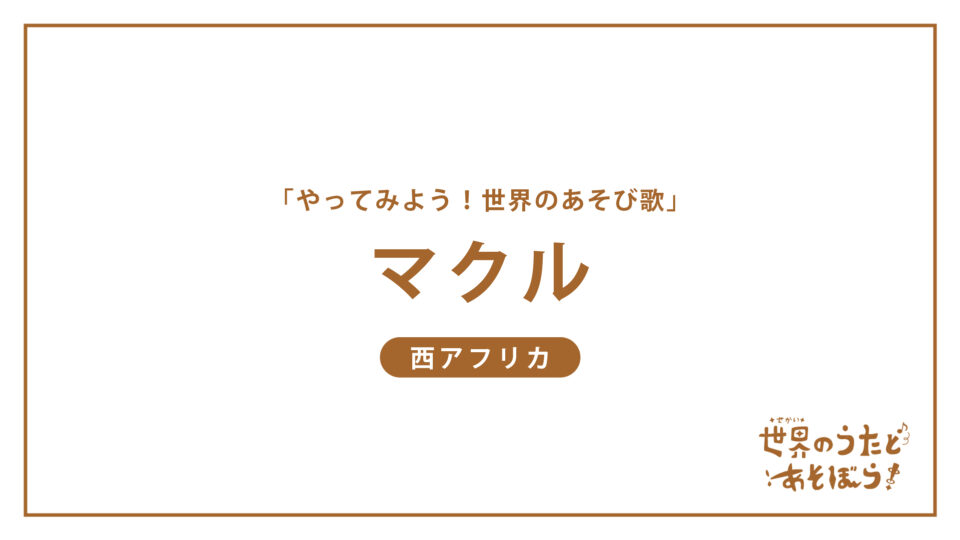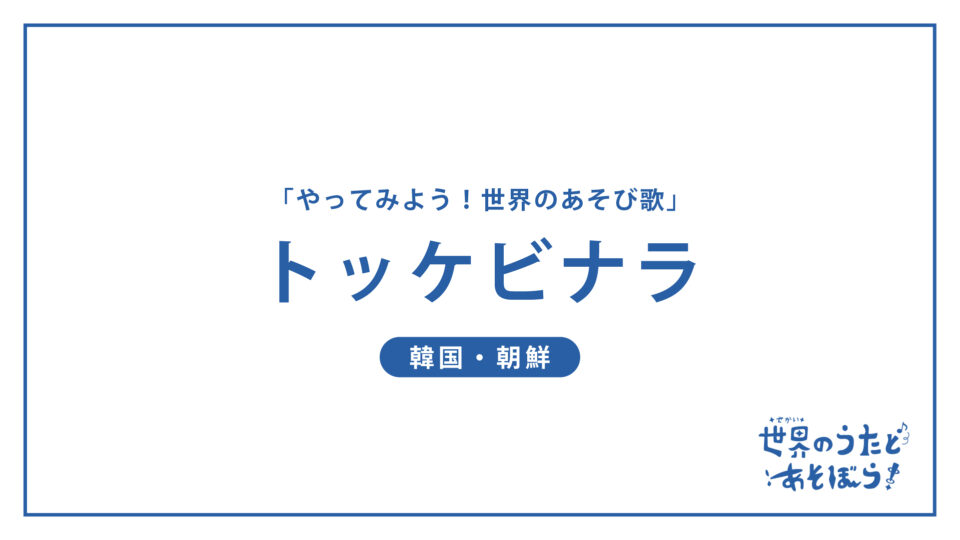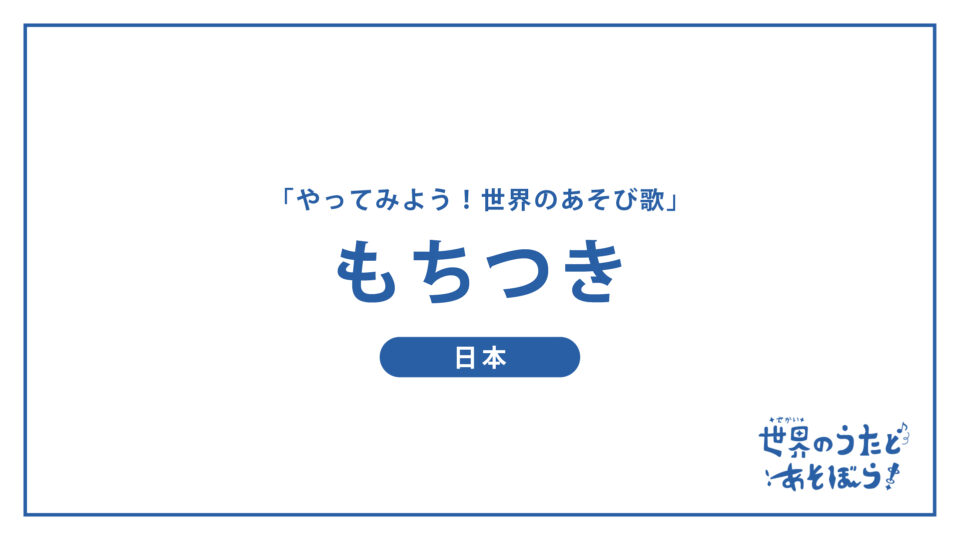茅ケ崎支援学校の教諭が取り組む「共生プロレス」――
テーマソングとともに颯爽と登場する、覆面のヒーロー。胸には“ともに生きる”の文字。ヒールレスラーの乱入に場内はざわつく。「お互いを知るためにプロレスをしよう」レフェリーに促されて対決が始まります。技がかけられるたびに客席はどよめき、声援を送る。ヒーローの必殺技が決まると、拍手が沸き起こり、いつの間にか客席と会場が一体となっていました。
「共生プロレス」と銘打つ活動を行うのは、神奈川県立茅ケ崎支援学校の教諭たち。地域のマルシェやイベントなどに参加し、プロレスを行っています。
応援にかけつけた生徒や保護者、さらに地域の人が“リング”となるマットレスの周りを囲みます。「年齢や障がいの有無を超えた様々な人たちでマットの周りに輪ができる。ここに仮の共生社会ができあがるんです。私達にとっては、マットの上ではなく、こうしてできあがる会場がリング。この輪を広げていきたい」と共生プロレスの発起人、同校総括教諭の小川和豊さんは語ります。
相手を受け止めることから始まるプロレスから広がる共生の輪
茅ヶ崎市の西北、西久保に所在する茅ケ崎支援学校。肢体不自由教育部門と知的障害教育部門があり、小学部から高等部まで約200名の児童・生徒が在籍しています。開校は1999年。20年以上経ちますが、地域の人に病院や高齢者施設に間違えられるなど、学校の存在が知られていないことに課題を感じていました。
「やがて子どもたちが出ていく地域社会の中で知られていないということは、彼らが地域で暮らすハードルをあげることになってしまうと思ったんです」と話す小川さん。学校のことを知ってもらう手段を考えていたところ出会ったのが、地域活性化を謳って活動する「ちがさきプロレス」でした。
「支援学校にゆかりのある覆面レスラーを登場させることで、同校のことを知ってもらうきっかけになるのでは」。そう考えていた矢先、プロレスラーを目指していた同校の若手教諭に出会います。教員たち自らがレスラーに扮し、「共生プロレス」と銘打った活動を始めることにしました。
そこで誕生したのが、ヒーローレスラー・きらめキッド。名前は、同校の校歌の歌詞や文化祭の名称に使われている馴染みのあるワード「きらめき」に由来しています。子どもたちのきらめきをまとって、共生社会をリングから訴えていくヒーローレスラーです。
音楽の先生が楽曲をつくり、レゲエシンガーの先生が作詞を担当。「一人ひとり違うから良い リスペクトでつながれば良い」共生社会を願ってつくられた歌は、一度聞いたら忘れられないメロディーです。
「どうしてプロレス?」と聞かれることもあります。「プロレスはお互いを知らないと試合にならない。まずは相手を受け止めるところから始まって、何度もぶつかりあいながらも理解を深めていく。違いを認め合いながらつながるところが共生社会と通じるところがあります」と話すのは、同校の共生社会推進専任教諭で、ヒーロー・きらめキッドとしても活躍する徳永翔さん。選手が観客の反応を引き出しながら試合を進めるプロレスは、リングの上だけではなくリングを囲む様々な人と一緒につくりあげるものです。プロレスを行うことで、リングの周りに集まった人が障がいの程度や状態にかかわらず一体となることに、共生社会実現への希望を感じていると言います。
試合の前説では、学校の紹介とともに、共生社会の大切さや、防災の知識、さらに人権についても伝えます。茅ヶ崎の民話「河童徳利」に由来した名前を持つレスラー、カッパトック・リーが訴えるのは、ゴミ問題や自然環境の大切さ。堅苦しくなく、伝えるのがモットーです。
回を重ねるごとにお客さんも増え、学校の児童・生徒のほか、保護者や卒業生も噂を聞きつけて来場するようになるなど、手応えを感じています。
「これからも学校を知ってもらうとともに、様々な人が共に生きる社会を推進していきたい。やがて子どもたちが暮らしやすい地域へとつながれば」と徳永さんは言葉に力を込めます。
今後もマルシェやイベントへの参加を予定している「共生プロレス」。多様な人や地域と関わりながら、共生の輪のさらなる広がりを目指しています。
校長・柏木雅彦先生コメント
子どもたちが地域の企業や社会福祉施設、イベントに参加できる、学びの場を開拓しています。生徒が育てたサツマイモを使って、茅ヶ崎で人気のアイスクリーム・プレンティーズさんが限定商品を製造した取り組みもそのひとつ。子ども達が地域に溶け込んでいくことで、地域の共生社会への理解につながっていくようにと願っています。